「遺言書はお年寄りだけのもの」「うちは揉めるほどの財産はないから必要ない」
そんな声をよく耳にします。
しかし実際には、遺言書がなかったために家族が長期間もめ続けるケースや、少額の財産でも感情的な争いに発展するケースが珍しくありません。
遺言書は、財産の多い少ないに関係なく、家族への想いを形に残すための重要な手段です。
この記事では、遺言書の基本的な意味から種類、作成時の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
遺言書とは?
遺言書とは、自分の死後に財産や権利を誰にどのように引き継ぐかを記した法的効力のある文書です。
民法で形式や効力が厳格に定められており、形式を守らなければ無効になることもあります。
遺言書の内容は大きく分けると次のようなことを記載できます。
- 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
- 遺産の割合や配分方法
- 未成年の子の後見人指定
- 相続人以外への財産の遺贈(例:友人や団体への寄付)
- 遺言執行者の指定(遺言の内容を実行する人)
遺言書を作るメリット
遺言書を作っておくと、以下のようなメリットがあります。
相続争いを防ぐ
遺言書がない場合、まずは法律で定められた割合(法定相続分)が分け方の基準となります。
ただし、相続人全員が合意すれば、この割合に限らず自由な分け方も可能です。
しかし、全員の合意を得るには時間や労力がかかり、「もっと欲しい」「不公平だ」といった感情的な対立が生まれることもあります。
遺言書であらかじめ明確に分け方を指定しておけば、このような交渉や争いを大幅に減らせます。
特定の人に多く渡せる
法定相続分とは異なる割合で財産を分けることができます。
例えば、介護をしてくれた子に多めに渡す、事業を継ぐ子に会社の株式を集中させるなどが可能です。
相続手続きがスムーズになる
遺言書があれば、相続人全員の合意を待たずに、銀行や法務局での手続きが進められます。
相続人以外にも渡せる
友人や内縁の配偶者、慈善団体など、法律上相続人でない相手にも財産を渡すことができます。
遺言書の主な種類と特徴
遺言書は大きく分けて次の3種類があります。それぞれ特徴が異なるため、自分に合ったものを選びましょう。
自筆証書遺言
自分で全文・日付・署名を手書きし、押印して作成する遺言書です。
- メリット
- 費用がかからない
- 思い立った時にすぐ作れる
- 内容を自由に書ける
- デメリット
- 書式不備で無効になるリスク
- 紛失・改ざんの恐れ
- 発見されない可能性
- 保管方法
2020年7月から「法務局での保管制度」が始まり、安全に保管できるようになりました。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
- メリット
- 法的に安全性が高い
- 紛失や改ざんの心配がない
- 手続きがスムーズ
- デメリット
- 手数料がかかる(財産額により異なる)
- 2人以上の証人が必要
- 予約や手続きに時間がかかる
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけ証明する遺言書です。
- メリット
- 内容を秘密にできる
- パソコンやワープロで作成可能
- デメリット
- 手間と費用がかかる
- 実務上利用は少ない
- 自筆証書と同様に無効リスクあり
種類別のメリット・デメリット比較
| 種類 | メリット | デメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書 | 費用ゼロ、手軽に作れる | 無効の可能性、紛失リスク | 手軽に書きたい人 |
| 公正証書 | 安全性が高く紛失防止 | 費用・証人手配が必要 | 確実に有効にしたい人 |
| 秘密証書 | 内容を秘密にできる | 費用・手間がかかる | 内容を知られたくない人 |
遺言書作成の注意点
遺言書は作れば終わりではなく、有効であることが重要です。
- 法律の形式を守る
日付・署名・押印など、法律で定められた条件を満たす必要があります。 - 最新情報を反映する
家族関係や財産状況は変わるため、5年に一度は見直しましょう。 - 保管場所を明確にする
自宅保管なら、相続人がすぐ見つけられる場所に。法務局保管制度も有効です。 - 感情的な偏りに注意
偏った分け方は争いを招く可能性があるため、慎重に判断しましょう。
まとめ
遺言書は、家族に安心を残すための「最後のメッセージ」です。
財産の多さに関係なく、誰でも早めに作っておくことがトラブル回避につながります。
自分の想いをしっかり伝えられるよう、適切な種類と正しい形式で作成しましょう。


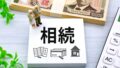

コメント